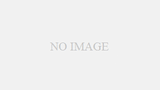記述試験対策が大切になる
最近の入試の傾向として、理科、社会とも記述問題を課している所が増えています。しかし、記号の選択や、暗記事項なら解答出来るのに、記述問題になると何を書いていいのか分からないとい理由で白紙にしてしまうお子さんも多いと思います。
記述問題が苦手だということは、その教科の内容に対して理解が不足しているということを、まずは認識してください。解法パターンだけ暗記していても、違った角度で問題が出題されると何も書けなくなる場合も、よく分かっていないまま覚えているだけという勉強法になっていることが多いようです。
理科の記述問題対策は観察や実験の機会を増やすことが大切
最近の理科の記述問題で多いのは、実験や観察の例をあげて、どのようなことが考えられるかを自分の言葉で書くようなものです。これは語句の暗記や問題集を解いているだけでは、なかなか身につきません。
まずは、教科書や資料集をしっかり見て、実験をする理由、器具の使い方、注意点、どういう結果が導きだされるかを、しっかり確認する癖をつけておきましょう。また、普段から動物や植物の生態に興味を持つことも大切になります。
最近は授業時間の減少で、学校で実験をすることが減っているようです。理科の実験キットも市販されているので、興味があれば家庭で実験を行ってみることも大切です。塾の学習が忙しくなる前の3年生から4年生のうちに、家庭で実験や観察をする機会を増やしてみてください。
理科の実験をするカリキュラムが組まれている塾もありますので、お子さんが興味があれば受講してみることをおすすめします。
↓漫画で理科の実験について学ぶことができます
 |
ドラえもんの理科おもしろ攻略 理科実験Q&A (ドラえもんの学習シリーズ) 新品価格 |
![]()
社会は資料の読み取りが出来るように
社会は資料を見て、考察する問題が多く出題されます。
対策としては普段の学習の中で、語句を暗記するだけでなく、1つのことに対していろいろな視点で考える習慣をつけることが必要になります。
例えば、青森がりんごの産地だと暗記するだけでなく、何故青森でりんごが取れるのかを、気候、地形、歴史などを考えるようにします。
歴史でも、「徳川家康が江戸幕府を開いた」と暗記するだけでなく、なぜ家康が天下を取れたのか、なぜ京都でなく江戸に幕府を開いたのかなどを、考えてみるようにしましょう。
また、家庭で時事問題に関心を持ち、家族で討論する時間を持つことも大切です。中学生で公民が分からないと言っている子どもに聞くと、親御さんが選挙に行かない、ニュースを見ない、新聞を読まないと言っていることが多いことが気になります。
政治や経済に関して考える訓練をすることは、生きていく上で大切なことです。今の日本の問題や政治、経済について、お子さんと話し合って一緒に考えてみるようにしましょう。また、時事問題対策に子ども新聞を購読することもおすすめします。
資料の読み取りは、基本的なグラフの見方、地図の見方、時代背景の知識なども当然必要になります。基礎的な知識をしっかり身につけた上で記述問題の対策をすることは言うまでもありません。
 |
社会科の記述問題の書き方: 10字から200字記述まで 解答までの手順がわかる (日能研ブックス) 新品価格 |
![]()
受験勉強で暗記事項が増えると、「考察する」時間がなかなか取れないですが、お子さんが興味を持ったことだけでもいいので、考えたり調べたりする時間が必要です。 考える訓練をと同時に、それを「文章に書く」練習もやってみてください。基本的な知識が身に付いていれば、解答例もしっかり頭に入ってくるようになります。